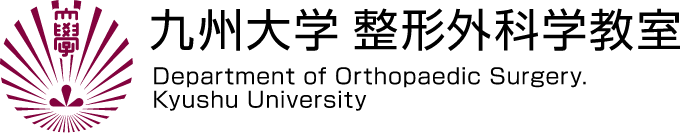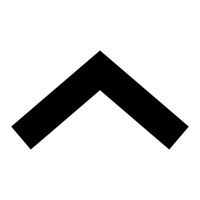1. 骨軟部腫瘍に対する重粒子線治療の保険適応化
昨年より九州国際重粒子線がん治療センター(通称佐賀HIMAT)において、肉腫に対する重粒子線治療が可能となり、患者さんの負担が大幅に軽減されました。それぞれの症例は、松本も班員を勤めております佐賀HIMATの重粒子線がん治療骨軟部腫瘍班で十分に検討され治療が行われています。さらに、本年度より悪性骨軟部腫瘍に対する重粒子線治療が保険適応となり、これまで以上に症例数が増加すると予想されます。しかしながら、当科での症例を検討した結果、脊椎・骨盤腫瘍に対する重粒子線照射後には約40%もの高い頻度で放射線骨壊死や骨折を来すことも明らかとなり、照射後の予防的固定術など、適切な治療法の開発を進めております。
2. 骨軟部腫瘍に対する新規薬剤の登場
これまで、軟部肉腫に保険適応のある薬剤は、アドリアマイシン、イフォマイドなど極少数のみでした。2012年に経口のmultikinase阻害剤パゾパニブが認可されたのを嚆矢に、2016年にはヨンデリス、ハラヴェンといった薬剤が次々と使用可能となり、これまで治療オプションのなかった進行軟部肉腫の患者さんにとって大きな福音となっています。さらに、骨巨細胞腫治療にもブレークスルーがございました。骨粗鬆症や転移性骨腫瘍に用いられている抗ランクル抗体(商品名ランマーク,プラリア)が骨巨細胞腫に対して著効することが、当科も参画した第II相臨床試験により明らかとなり、これまで切除困難であった脊椎・骨盤発生の骨巨細胞腫に対する治療法を一変させました。(Annal Oncol, 2015) 実際に投与してみると、骨硬化を伴った腫瘍活動性の劇的な低下を認め、その効果には驚かされます。しかし、適切な治療の継続期間が不明な点や、二次性悪性化の報告など解決すべき問題も多く、今後さらなる研究が必要です。上述の薬剤は、いずれも独特の作用機序を持ち、それぞれの使い方にまだ明確なガイドラインはありません。教室では各薬剤を用いた基礎的研究も既に開始しており、今後は生物学的にメカニズムに基づいた治療法を確立して行く予定です。
3. 多施設共同研究の推進
全国レベルでの骨軟部腫瘍の治療成績の改善と、日本から発信する世界に通用するエビデンスの確立を目指し、多施設共同研究も推進しております。岩本先生が班長をお務めになる国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の研究班で、複数の臨床試験を遂行・立案しています。骨腫瘍に対しては骨軟部腫瘍領域で本邦初の第III相臨床試験である「骨肉腫術後補助化学療法におけるIFO併用の効果に関するランダム化比較試験(JCOG0905)」を、軟部肉腫に対しては「高悪性度非円形細胞肉腫に対するIFO+ADMによる補助化学療法の第II相臨床研究(JCOG0304)」に引き続く非円形細胞肉腫を対象としたゲムシタビンとドセタキセル(GEM+DTX)による補助化学療法の第Ⅱ/III相臨床試験を実施しており、教室からも順調に症例を登録中でございます。さらに、骨巨細胞腫に対するランマークの術前投与の妥当性や、高齢者の高悪性度骨腫瘍に対する化学療法の有効性を検証する新規試験が計画中であり、次年度からの開始が予定されています。
免疫チェックポイント阻害剤を用いた腫瘍免疫療法、全ゲノムシークエンスによるテーラーメード医療の現実化など、がん診療はかってない程のスピードで変化を遂げております。それらの進歩を取り入れながら、今後も教室の伝統ある骨軟部腫瘍の臨床・研究をさらに発展させていく所存であります。